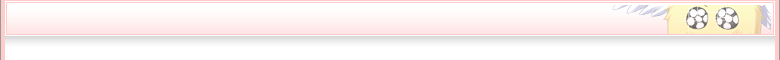|
『……ラフル〜』
『あぁ、おはよう』
『ララ、ラフル〜ル?』
『余計なお世話だ。なんか目が覚めちゃったんだよ』
『ラフ……ラフール?』
『雨なんぞ降らん! ったく、朝から絡むなよ……』
既に居間のテーブルには食器が並べられており、ラフルは急がしそうに飛び回っている。眠気を覚まそうとポットを覗き込むとお湯が入っていなかった。ポットに水を注ぎながら、抜けているところが逆にラフルらしいなと思った。
コーヒーが飲めない以上はこれ以上やる事が無く、ソファーに寝そべりながらテレビをつけた。ニュースの時間だった。
何気なく視線をテーブルに戻す。と、目の端にパンが入った袋をラフルがテーブルに運んでいるのが見えた。軽めのBGMと共にCMが切り替わり、キャスターとお天気お姉さんがお喋りを始める。
だが、俺はラフルの一挙手一投足に集中していた。
長年の謎が今、解明されるかもしれない。
毎日用意されているあのトースト、ラフルはあのちんまい手で一体どうやって焼いているのか──?
俺が固唾を飲んで見入っていると、それに気付いたラフルがこちらに向きなおった。
『……ラフル!』
『ん? いや、上手にパンを持ってくるな〜と思って』
『ララ、ラフール!』
『早く起きたんだから、手伝ってくれって? やだよ』
『ラフラァアア! フラァアア!』
『断る。お前だいたい、俺の世話係なんだろ? お前が支度するのが当然だろ!』
ラフルが俺の眼前に迫ってきた。
俺の周りをパタパタと行ったり来たり、うざったい事この上無い。
『ボックン、世話係じゃなくてお目付け役……』
『……いきなり喋るなよっ!!』
『ご主人タマ、早く起きたなら手伝うのがスジだぜぇ』
『だーかーらー……断るって言ってんだろ』
俺の迷惑そうな顔が癇に障ったのか、ラフルの語気が荒くなっていく。
『……ボックン一人だけ働かせて良心は痛まないの?』
『全く痛まない。あとラフル、それ以上喋るな。また人前で喋って大騒ぎになるだろーが!』
『ラフラァアア!』
『ぐあっ! ……なんだよ朝っぱらから!!』
急に視界が真っ暗になったかと思うと顔に激痛が走った。
ちょっと遅れて意識が一瞬飛びそうになる。
どうやら怒ったラフルが俺の顔に目掛けて体当たりをしてきたようだ。
『わ、わかった、わかったよ。そうだよね、自分で食べるものだからね。自分で作るの当然だよね!』
『ラフル! ラフル!』
『んじゃ俺はコーヒーいれるから、ラフルはトーストを焼いてくれ』
『……ラフ〜ル……』
俺はムクれているラフルを抱えて、頭を撫でた。謎を解明すると言う目的がある以上、ここでヘソを曲げられるのは避けたかったのだ。不満気なラフルをゆっくりとソファーに下ろして棚の前まで移動する。そしてコーヒーカップを取り出しインスタントの紙パックの口を開いてカップに乗せた。
ラフルはまだ何か言いたそうだったが、俺の様子を見てパタパタと羽を震わせるとテーブルの上で袋から食パンを引っ張り出しはじめる。危うくまた見入りそうになったが、さっきと同じ状態になってしまっては元も子もないので仕方なく視線を外してポットの前まで移動した。
(あの、手だか足だかわからん物では、絶対にトースターのタイマーは回せない筈。つまり……つまり……どうやってるんだろうか?)
うぅ、見たい。
俺が横目でラフルを見ると丁度トースターにパンを入れているところだった。見るタイミングが早かったか、そう思いつつもちらちらと見ているとラフルがそれに気がついてしまった。
『……ラフル?』
『ああいや何でもない、何でもないほんとに何でもないから続けてくれ』
『ラ〜フ〜ル〜』
『だからサボってる訳じゃないよ、わかってるって!』
慌てて俺はポットの方に向き直り『お湯を注ぐ』ボタンを連打した。と、その拍子にカップが横にスライドして注がれるべきお湯が──俺の足に注がれてしまった。
『……アチ、アチチチチッ!! ホアッチャーッ!!』
|